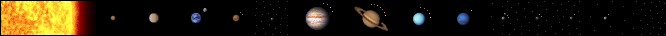天王星
この記事は英語版、フランス語版、アラビア語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2022年2月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。
|
| 天王星 Uranus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||
| 仮符号・別名 | ハーシェル(Herschel) | ||||||
| 分類 | 天王星型惑星 | ||||||
| 軌道の種類 | 外惑星 | ||||||
| 発見 | |||||||
| 発見日 | 1781年3月13日[1] | ||||||
| 発見者 | ウィリアム・ハーシェル[1] | ||||||
| 発見場所 | |||||||
| 発見方法 | 自宅の望遠鏡による観測 | ||||||
| 軌道要素と性質 元期:J2000.0[1] | |||||||
| 軌道長半径 (a) | 19.19126393 au[1] | ||||||
| 近日点距離 (q) | 18.286 au | ||||||
| 遠日点距離 (Q) | 20.063 au | ||||||
| 離心率 (e) | 0.04716771[1] | ||||||
| 公転周期 (P) | 84.25301 年 | ||||||
| 会合周期 | 369.66 日[1] | ||||||
| 平均軌道速度 | 6.79km/s[1] | ||||||
| 軌道傾斜角 (i) | 0.76986°[1] | ||||||
| 近日点黄経 () | 170.96424°[1] | ||||||
| 昇交点黄経 (Ω) | 74.22988°[1] | ||||||
| 平均黄経 (L) | 313.23218°[1] | ||||||
| 太陽の惑星 | |||||||
| 衛星の数 | 28[2] | ||||||
| 物理的性質 | |||||||
| 半径 | 25,559 km(赤道)[1] | ||||||
| 表面積 | 8.13 ×109 km2 | ||||||
| 質量 | 86.811 ×1024 kg | ||||||
| 地球との相対質量 | 14.54[1] | ||||||
| 平均密度 | 1.270 g/cm3[1] | ||||||
| 表面重力 | 9.01 m/s2[1] | ||||||
| 脱出速度 | 21.30 km/s[1] | ||||||
| 自転周期 | 17時間14分 (0.7183 日) (逆行) | ||||||
| アルベド(反射能) | 0.300(ボンド)[1] 0.488(幾何)[1] | ||||||
| 赤道傾斜角 | 97.77°[1] | ||||||
| 表面温度 |
| ||||||
| 大気の性質 | |||||||
| 大気圧 | 深さによって異なる | ||||||
| 水素 | 83% | ||||||
| ヘリウム | 15% | ||||||
| メタン | 1.99% | ||||||
| アンモニア | 0.01% | ||||||
| エタン | 0.00025% | ||||||
| アセチレン | 0.00001% | ||||||
| 一酸化炭素 硫化水素 |
微量 | ||||||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |||||||
天王星(てんのうせい、Uranus)は、太陽系第7惑星である[3]。太陽系の惑星の中で木星・土星に次いで3番目に半径が大きく、木星・土星・海王星に次いで4番目に重い。1781年3月13日、イギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルにより発見された。名称は、ギリシア神話における天の神ウーラノス(Ουρανός、ラテン文字転写: Ouranos)のラテン語形である。
最大等級+5.6等と地球最接近時は肉眼で見える明るさになることもあり、ハーシェルによる発見以前にも恒星として20回以上観測されていた(肉眼観測も含む)。
物理的性質[編集]
内部構造[編集]

天王星は主にガスと多様な氷から成っている。地球上の氷は液体の水が冷えて固まったものを指すが、天文学ではメタンやアンモニアでも氷という。大気には水素が約83%、ヘリウムが15%、メタンが2%含まれている[4]。内部は重い元素に富み、岩石と氷からなる核のほか、水やメタン・アンモニアが含まれる氷からなるマントルで構成されていると推測されている。酸素・炭素・窒素が多く含まれ、ほとんどが水素とヘリウムで出来ている木星や土星とは対照的である。天王星と海王星は従来木星型惑星に分類されていたが、木星や土星の核から液体の金属水素の層を除いたものによく似ており、内部は比較的均一に分布しているようである。こうした違いから、木星型とは異なる天王星型惑星(英: ice giant)として分類されるようになった。
自転軸[編集]

天王星の特徴の一つとして、自転軸の極端な傾きが挙げられる。天王星の赤道傾斜角は約98度、つまり黄道面に対しほぼ横倒しとなっている[5]。加えて、公転周期が約84年なので、即ち極点では昼と夜がそれぞれ約42年間続くということになる。
天王星の自転軸がなぜこれほど傾いているのかは判明していない。古典的な推察として、星がまだ完成されていない時期に、大きな原始天体が衝突したという説(ジャイアント・インパクト説)や、かつて巨大衛星が存在しており、その引力の影響で徐々に傾斜していったという説も唱えられている[6][7]。また、天王星が現在のように自転軸が公転面に対して横倒しになるには、地球サイズの天体が1回ではなく、2回衝突する必要があることがシミュレーション研究により判明したとの報告もある[8]。
天王星は自転軸の傾きのため、極周囲の方が赤道周囲よりも太陽からの熱を受けているが、後者の方が前者よりも温度が高い。この理由もまだ解明されていない。
大気[編集]
天王星が青緑色に見えるのは、上層大気に含まれるメタンによって赤色光が吸収されるためである。ただし、色は公転に伴って変化する。そのため、天王星には季節変化があると推測されている。
天王星の大気は、他のガス惑星と比べると雲がほとんど見られない、特徴の少ないのっぺりとした外観を持つ。これは、横倒しになった自転軸の影響で、昼夜での気温変化がほとんどないためである。しかし、2007年に天王星は春分を迎え、赤道方向に太陽光が当たるようになると、通常の惑星と同じような昼夜の繰り返しが起こるようになったため、気温変化が起こるようになった。実際、2011年に北半球でかなとこ雲に相当する白い雲が観測された。これは、メタンの氷で出来た雲と考えられている[5]。
磁場[編集]

ボイジャー2号によって、天王星に磁場の存在が確認された。その強さは地球とほぼ同じである。しかし地球や木星とは大きく異なる特徴として、磁場の中心は惑星の中心から大幅にずれており、また磁場の軸が自転軸から60°も傾いている。そのため、地球のそれよりずっと大きく変動するとされる。ヴァン・アレン帯も土星並みに強く、内側の衛星や環に存在するメタンは、強い化学変化を受けて黒っぽく変色してしまう。
2011年11月、ハッブル宇宙望遠鏡が天王星のオーロラ嵐を2度にわたって観測した[9]。
発見[編集]

天王星が惑星として確認されたのは近代になってからである。実際には何度も観測されてはいたが惑星とは認識されていなかった。知られている観測例は、1690年にジョン・フラムスティードがおうし座34番星として記録したものが最古である。
1781年3月13日、ウィリアム・ハーシェルが天王星を観測した。彼はそれが新天体であることには気づいたが、彗星だと考え、同年3月22日に彗星を発見したと発表した。しかしその後観測が進むと、彗星だと仮定して求めた軌道は観測に合わなかった。そこで、アンデル・レクセルは円軌道を仮定して軌道を求め、観測結果を説明することに成功した。求められた軌道長半径は18.93auで、新天体は土星のはるか遠方の、それまで思われていたよりもずっと巨大な天体であることがわかった。これ以後、新天体は惑星と見なされるようになった。
ハーシェルは新惑星をイギリス国王ジョージ3世にちなみ、ゲオルギウム・シドゥス(Georgium Sidus、ラテン語で「ジョージ星」の意)と名付けた(のちに、sidusは恒星であって惑星ではないという指摘を受け、ジョージアン・プラネット(Georgian Planet)に改名)。しかし、イギリス以外では普及しなかった。1784年にジェローム・ラランドが提案した「ハーシェル」は、フランスの天文学者の間に広まった。その後も多くの名前が提案されたが、最終的に、ヨハン・ボーデが提案、空の神ウーラノスに由来する「ウラヌス」が広まった。1827年までにはイギリスでもこの名が最も一般的になり、全ての天文台がウラヌスに切り替えたのは1850年だった。なお、中国で生まれた「天王星」という訳語が、日本・韓国・ベトナムにも広まった。
惑星探査[編集]
天王星に接近した宇宙探査機は、1977年8月20日に打ち上げられたアメリカ航空宇宙局のボイジャー2号のみである。ボイジャー2号は1986年1月24日に天王星に最接近し、天王星のほか、環や衛星を撮影した。
日本では、1970年代にN-Iロケットを使用した探査が検討された[10]が、当時はスイングバイ技術を有していなかった事や観測衛星の性能不足などから実現しなかった。
衛星と環[編集]

天王星には2024年2月23日の時点で28個の衛星が発見されており、そのうち27個が命名されている[2]。衛星の名前はウィリアム・シェイクスピアかアレキサンダー・ポープの作品中の登場人物名がつけられている(24個がシェイクスピア関連である)。
ボイジャー2号が接近するより前に発見されたアリエル・ウンブリエル・チタニア・オベロン・ミランダ[5]を天王星の5大衛星と呼ぶことがある。
衛星の他に、直径10m以下の暗い物質で構成された薄い環もある。天王星の環に関して最初に言及したのは惑星本体の発見者でもあるウィリアム・ハーシェルであった。ハーシェルは1789年2月22日[11]に「赤みがかった」環(ε環と推測される)を観測し、1797年に正式に発表した。だが、この説は受け入れられず、その後約200年にわたり環は観測されなかった。1977年3月10日にカイパー空中天文台から恒星の掩蔽を観測する事によって天王星の環は発見された。その環は暗く、とてもハーシェルの時代の望遠鏡で見えるものではないと思われたが、後にカッシーニによる観測で土星の環が拡散しつつあるという事が分かったため、ハーシェルは天王星の環を実際に観測していたが、その後2世紀の間に環が暗くなってしまったのではないかという仮説が立てられている[12]。
天王星の写真に写る輪は一般に鮮やかな色をしているが、これらは殆どが赤外線域で撮影された輪を可視光域の写真と合成したり、あるいは写真そのものが赤外線域で撮影されたものである。可視光では前述の通り非常に暗い為に、輪が明瞭に撮影される事はまず無い。
2007年には、天王星の環が地球から見て真横を向く位置になった[13]。天王星では公転周期の半分にあたる42年に一度の出来事である(環が真横を向くのは木星では6年、土星では15年に一度)。また衛星やその影が惑星と重なるのは木星や土星ではよく見られる光景だが、この時にハッブル宇宙望遠鏡によって天王星と重なるように通過する衛星とその影の画像が撮影された。
人類との関係[編集]
歴史と神話[編集]
ウラヌスは古代人の命名ではなく、近世以降に発見された惑星に、他の惑星に倣い「未使用の神話上の大物」の名が付けられたもので、天体の外見や運行上の特徴と付けられた神名の関わりは希薄である。なお、Uranusはギリシア神話に由来する名称であり、他の惑星がローマ神話に由来する名称を与えられていることから本来は天王星もカエルス(Caelus)と命名されるべきであったが、それはローマ神話で対応する名称が忘れ去られてしまうほどこの神の存在が人々の記憶から希薄になっていたことを意味する。ウラヌスはギリシア神話の主神ゼウスの祖父にあたる。中国(東洋天文学・占星術)では未発見のため名称がなく、ウラヌス=天空神を翻訳して天王星とした。
占星術[編集]
10大天体の1つである。10大天体は、20世紀の冥王星発見後の占星術のもの。天王星が発見されたのは18世紀後半でありそれ以前にはありえないため、七曜・九曜にも含まれない(九曜は別の「仮説上の天体」をカウントする)。
西洋占星術では、宝瓶宮(みずがめ)の支配星で、凶星である。変化を示し、改革・離別・不安定・電撃に当てはまる[14]。
惑星記号[編集]

ウラヌス=天王星と改称される以前は、発見者にちなみ「ハーシェル」と呼ばれたため、ハーシェルの「H」を他の惑星記号に似せて図案化したものが、占星術・天文学を通して用いられていた。これが改称後も用い続けられている。
関連作品[編集]
ギャラリー[編集]
-
地球との大きさ比較。
-
赤線が天王星の公転である。
脚注[編集]
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s “Uranus Fact Sheet”. nssdc.gsfc.nasa.gov (2023年5月22日). 2023年8月25日閲覧。
- ^ a b “惑星の衛星数・衛星一覧”. 国立天文台 (2024年2月23日). 2024年2月23日閲覧。
- ^ “442年ぶり皆既月食中に惑星食、次回は322年後の天体ショー 8日夜、天気よければ各地で”. 日刊スポーツ (2022年11月5日). 2022年11月8日閲覧。
- ^ Uranus Fact Sheet NASA
- ^ a b c 天王星の基本情報 Jaxa 宇宙情報センター
- ^ Ker Than (2009年12月4日). “Large moon of Uranus may explain odd tilt”. New Scientist 2010年4月8日閲覧。
- ^ Boué, G. & Laskar, J. (2010). “A Collisionless Scenario for Uranus Tilting”. The Astrophysical Journal 712 (1): L44-L47. doi:10.1088/2041-8205/712/1/L44.
- ^ AstroArts 天王星の自転軸が傾いたのは2回の天体衝突が原因? AstroArts Inc 記事:2011年10月12日
- ^ ナショナルジオグラフィック ニュース 天王星のオーロラ、ハッブルが初撮影
- ^ 竹中幸彦、斉藤勝利、Nシリーズ・ロケットによる惑星探査の可能性について 日本航空宇宙学会誌 Vol.26 (1978) No.288 P.36-42
- ^ Uranus rings 'were seen in 1700s' BBC 2007年4月18日
- ^ ハーシェルは天王星のリングを見たか RAS Press News 2007年4月27日
- ^ 天王星の環、発見後初めて真横を向く AstroArts 2007年8月30日
- ^ 石川源晃『【実習】占星学入門』 ISBN 4-89203-153-4
参考文献[編集]
- 『太陽系はここまでわかった』リチャード・コーフィールド著、水谷淳訳、文芸春秋、2008年
関連項目[編集]
- コールド・ネプチューン
- オリオン座15番星 - 天王星から見れば南極星となる。
- ウラン - 天王星に因んで命名された元素。
外部リンク[編集]
- 理科ねっとわーく 太陽系図鑑(天王星) - ウェイバックマシン(2021年12月10日アーカイブ分)
- 国立科学博物館 宇宙の質問箱(天王星・海王星)
- ザ・ナインプラネッツ 日本語版(天王星)
- The Nine Planets Uranus Facts - ザ・ナインプラネッツ 原語版(天王星)(英語)
- 『天王星』 - コトバンク
- Voyager Uranus Science Summary(英語)NASA/JPL