ヨーロッパ宝飾芸術の源流をたどると、世界の宝飾芸術が文化と共に変化を遂げてゆくドラマチックな過程が浮かび上がり、宝石は経年変化することなく残っている事実にも感動します。
世界の宝飾芸術をたどっていくため、シリーズとしてまとめました。
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー1【古典期から近世へ解説】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー2【中世からルネサンスの時代】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー3【ネオ・クラシシズムまで】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー4【近世以降からセンチメンタリズム】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー6【ジュエリーデザイナー】
ヨーロッパの宝飾芸術の宝石ジュエリー10【エドワーディアンから】
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術の源流【宝石とジュエリーの歴史】についてすぐわかるヨーロッパの宝飾芸術 著者山口遼 発行 東京美術から引用して解説します。
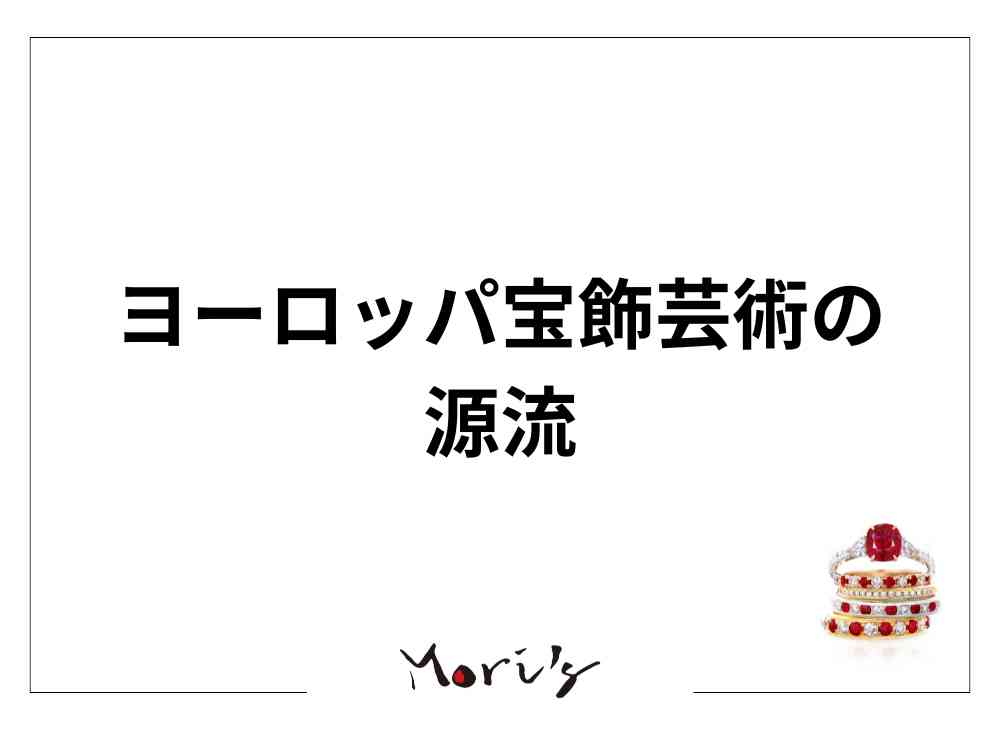
古代エジプト【数千年一貫して変わらない様式政教一致の威厳に満ちた美術品】
王と神を荘厳化するための装身具
紀元前525年にペルシア帝国に服属する以前の古代エジプトは、今から5千年前の早期王朝時代にまで遡るが、極めて特徴的であるのは、その長い期間にわたって美術様式にほとんど変化が見られないことである。
政教一致国家であったことから、美術品も純粋な美のためのものではなく、有目的なものであった。王であり神である人物を尊厳化し、その死後は神殿や葬祭殿に埋葬して、カーと呼ばれる魂が帰るのを持つ遺体を飾る品物であった。美術品の中でもきわめて大きな地位を占め、墓地に埋められたこともあって膨大な数の装身具が今に残る。
象徴性を持つモティーフと鮮やかな色彩
驚くべきことに、現在使われているジュエリーのほとんどは、ブローチを除いて、この古代エジプトに登場している。今でも少数派に属するアンクレットすら、使われてる。
素材としては金が中心で、天然塊の少ない銀はあまり作例がない。宝石の類も使われており、基本は色の鮮明などラピスラズリ、コーネリアン、トルコ石などで、まれにガラスも見られるが、最も特徴のある素材はフィアンスと呼ばれる一種の焼き物である。
これは石英の粉末に油を加えて成形し、その上に色釉(普通は明るいブルー)をかけて焼いたものだ。自由に成形できるために、立体像のものが多い。
使われているモティーフは、スカラベや鷹、蓮の花、パピルス、邪悪なものをはねつける力を持つウジャットと呼ばれるホルスの神の目、そして太陽を昼から夜へ運ぶはしけなど、すべて何らかのシンボルであるもののみである。
ジュエリーの細工には、金線の間に色のある素材を入れてデザインとしたものが多く、一見すると後の有線七宝のように思われるが、そうではなく色石をカットして嵌入したものだ。
この頃すでに金を銅板や皮革の間に挟んで石で薄板をたたき出す方法やその板をねじって金線を作る方法、さらには粒金を作るための溶剤技術もマスターしていた。デザインこそ神と宗教とに支配されていたものの、エジプトのジュエリーに使われている技術とその精度の高さとは、これが人類最古のジュエリーとは思えない見事なものである。
メソポタミア【20世紀に発掘された最古の遺物打ち出しと線刻模様の金銀細工】
繰り返された諸王国の興亡
メソポタミアとはギリシャ語でふたつの川の間という意味だが、ティグリスとユーフラテス川を中心とするこの一帯は、古代からシュメール、バビロニア、アッシリアなどの諸王国が数千に渡り興亡を繰り返した。ジュエリー史の上では、シュメールの一都市ウルの遺跡から出た金銀細工が最も有名である。
しかし発掘が着手されたのは1900年前後、ウルの発見は1922年のことに過ぎず、この金銀細工あるいはジュエリーは、われわれにとっても最も新しい古代ジュエリーであると言える。
特徴的な技法で作られた金の頭飾り
1926年から31年にかけて発掘されたウルの金銀細工の最大の特徴は、金属の板を裏から打ち出したルプセや表から線刻模様を打ち込んだチェイシングの技法によるものが多いことで、代表例yとされる女王プアビの金の頭飾りなども、打ち出しだけで溶接の跡は全くない。また金の他にも銀が、石としては青のラピスラズリやオレンジっぽい赤のコーネリアン、白と赤のサードオ二クスなど混合して使われ、複雑な色合いを出すのに成功している。
こうした素材はメソポタミアでは産出せず、遠くイランあるいはそれよりも以東の地から運ばれたものと推定されている。これらのカラフルな素材を糸に通したネックレスが一番多く、単に色を楽しむものとしてだけでなく、石の持つ呪術的な効用が期待されていたらしい。
メソポタミアで発生したもうひとつのユニークなものは、シリンダー・シールであろう。これはラピスラズリや貝殻等を、中心に孔を開けた円盤状に加工し、円筒の表面にさまざなな模様を彫り下げたものである。孔に棒などを通したそれを、粘土板などの上に押し付けながら回転冴えると、陰刻された模様が逆に陽刻のパターンとして残る。彫られた模様としては、古いものでは宴会や戦闘の場面が多く、やがて動物の群れや動物を操る人間の像が増える。これは実用の具であったようで、石や粘土に刻まれた文章の正統性を示す一種の印章であったと推定される。
メソポタミアの金銀細工はウルのものだけでなく、シュリーマンが1873年に発掘して、トロイ戦争の頃のものと決め付けた、いわゆるトロイの違宝も今では、トロイ戦争よりも千年以上も古い、古代メソポタミア諸王国のいずれかのものと推定されている。人類最古のジュエリーの源流のひとつがこれほどに多様であり、それがつい最近まで全く知られていなかったろいうのも、歴史の皮肉として面白いものがある。
古代ギリシャ 【自然と人間をモティーフとした工芸色彩として七宝を発明した文明】
クレタ文明を継承したミケーネ文明
クレタ島に起源前3千~2千年紀に栄えたものをクレタ文明(ミアノ文明とも言う)、それをギリシャ本土で継承したものをミケーネ文明と呼ぶ。
クレタ文明の工芸の面白さは、動物や人間、草花などのモティーフを動きを中心に捉えたことで、生き生きとした表現の物が多い。
大きな彫刻類はないが、フィアンスや象牙、石のインタリオや金の板の打ち出しなどに優れたものが多く、いわゆるトロイの遺宝と呼ばれるもののなかに優品が多い。七宝もまた、ミケーネが起源とされる。
周辺民族との関わりを窺わせるデザイン
トロイの遺跡を発見した後、シュリ―マンは1876年、ミケーネの王宮の発掘にも成功する。17本もの縦杭の墓地から発見された金銀製品は、総計で13.5キロにも及ぶ。そのなかで最ユニークなのが、死者の顔にかけたと思われる金製の仮面状の装身具で、思い込みの激しいシュリ―マンは、これをトロイ戦争でギリシャ軍を率いたアガメムノン王のものと決め付けたが、実はそれよりも300年以上も昔のミケーネ時代のものであった。同様のものが6枚発見されていることからして、一定の地位以上の死者への礼儀であっただろう。作りとしては簡単なもので、金の板をルプセによって作ったものにすぎない。
このほか現存するジュエリーには、人物像や神と人々の集まり、動物などを金の板の表面にインタリオ状に掘り下げたシグネット・リングと呼ばれる指輪がある。これはその後もヘレニズム期まで作り続けられたが、金だけによるものが中心で、彫りは鋳込みではなくすべて手彫りである。宝石類はインタリオを施した円筒や指輪のシール(封蝋)などに見られる程度で、ほとんど使われていない。ジュエリーに必要な色彩は、彼らの発明とされる七宝を主に使ったようである。
また、周辺民族との関わりを示すのが、動物文(神聖動物であった牛が多い)や動物闘争文などの使用と、クレタ島のヘラクリオン美術館にある蜂のペンダントに見られるような粒金技術の多用である。このあたりは、古代ギリシャが西欧よりも中近東諸国とのつながりが密接であったことの証拠であろうか。
これから先、古典期からヘレニズム期を経てローマ属州になっても、ギリシャ人は周りの国々を含めた諸国の金銀細工師として働く素地が、すでにこの時期に生まれていると言える。
エトルリア【ジュエリー史上最大の謎 謎の民族が残した粒金細工】
遺物が物語るエトルリア人の工芸の才
エトルリア人とは、今のイタリアのトスカナ―地方を中心とする地域に、紀元前7~1世紀にロマに併合されるまで住んでいたイタリアの先住民族のひとつである。エトルリア人の特徴はあるゆる工芸に秀でていたことで、特に、金銀細工や青銅細工、テラコッタなどに発揮され、膨大な遺物が今に残る。しかし、文字を持たなかったために、その言語や生活、宗教については今も不明なことが多い謎の民族である。
優れた具象表現、例を見ない金の装身具
彼らは文字を持たなかったせいなのか、あらゆる物を精密な具象の作品として作ることに天才的な能力を発揮した。なかでも金による装身具は、それ以後の人類の歴史に例を見ないものだ。
エトルリア人の作ったジュエリーの特徴は、金以外の素材、特に宝石類の使用をほとんどしないこと、その代わりに、金製品の表面に驚くほどに微細な粒状の細工を施したことにある。このミリ単位以下の金細工を、粒金あるいはグラニュレーションと呼ぶ。
これは直径1ミリ以下、最小のものでは実に0.18ミリという小さな金の粒を、別の金の板に貼り付けて模様を描く細工だが、金の粒を貼り付けるのがどうしてそんなに大変なのかと思うのは素人。まず普通の蝋材は粒を埋めてしまうので使えない。それに粒同士が接近しているのだから、ひとつひとつ付けていたのでは前に付けた粒が熱ではがれてしまう。つまり、この無数の金の粒は、すべて一度に接着してあるのだ。
加工に使う熱と言えば木炭を焚くだけの時代に、どうしてここまで精緻な加工ができたのか、ジュエリー加工の歴史上最大の謎のひとつとされる。おそらく、金の粒と板の間にある種の素材(かのプリニウスによれば魚の油)を置くことで融点を下げて接着したらしく、その後さまざまな職人がこれに挑戦しているが、本当のところは今でも謎のままである。
エトルリア人が遺した膨大な数のこうした金細工は、今でもイタリアの土中から出てくるほどである。言語や歴史すらはっきりしない民族が残したもの、それが粒金のジュエリーである。
スキタイ【古代オリエントとギリシャの影響表現は騎馬民族ならではのもの】
ロシアの草原地帯を遊弋した騎馬民族
スキタイとは、紀元前7~3世紀頃に、黒海の北岸からドナウ川あたりまでの勢力圏とした騎馬民族の名前。
さまざまな民族との抗争あるいは混合により盛衰を繰り返したものと思われるが、詳細は不明である。金属細工にきわまえて優れ、そのクルガンと呼ばれる高塚からの出土品には、世界の古代文化のなかでも筆頭のものと言える金細工品が多く含まれる。スキタイ文化は、前7~5世紀の前期と全4~3世紀の後期と分かれるが、前期のものには古代オリエントの、後期のものにはギリシャの影響が色濃い。
特徴的な動物文と移動に適した装身具
前期、後期を通じて共通するのは、デザインが動物、あるいは動物同士の争いを描いたものが中心であることだ。前者の動物文、後者を動物闘争文と呼ぶが、これはいかにも遊牧を主とする騎馬民族ならではのデザインといえよう。また、馬に乗って移住することが常であった民族固有のことだが、移動に際して邪魔にならないようアップリケ状に衣服に縫い付けて使うジュエリーが多数あり、逆にイヤリングやブローチ、ブレスレットといった移動生活にとって不便なものはきわめて少ない。
前期のジュエリーは金と銀、それにブロンズ製である。デザイン的にはほとんどが動物または人間と動物の関りに限定され、技法的にも金の場合は薄板への打ち出しに、ブロンズの場合は多くが鋳造に限定され、宝石類の使用はほとんどない。
これが後期にのものとなると一転してギリシャ風のデザイン、つまりアンフォーラや女神像、動物像を先端に付けたトルク、人物像江尾彫った指輪などが登場する。
宝石も少ないながらガーネットやコーネリアン、ガラスなどが使われる。とは言え、数の上ではやはり動物文様の金製品が圧倒的に多い。ただそれらも前期のシンプルな作りのものと比較すると、技術的にきわめて高度となる。
こうした後期の金細工品が、黒海沿岸にまで植民したギリシャ人の工人によって作られたのか、あるいは技術を学んだスキタイ人が作ったのかは、専門家の間でも意見が真っ二つに分かれる。
国立ウクライナ歴史宝物館が所有する胸飾りには、首をひねる。これは中空の金管が4本走り、その間に、上には動物を飼う人間像が、中間には金の貼り付けで連続花模様が、そして一番下には互いに噛み合う動物文、つまり動物闘争文の恐ろしいまでに精緻な作りで表現されたものが支配されている。これなどは、デザインはスキタイ、作りの技術はギリシャと推測されるが、さてどのような状況でこのすごい胸飾り(世界中の金細工品でベストテン入り間違いなし)は作られたのか、いろいろの説が考えられる楽しい作品である。
ケルト【さまざまな金属製品を作り上げたヨーロッパ最古の民族のひとつ】
英国やアイルランドに渡った海のケルト
ケルトとは、ヨーロッパ人の最も古い祖先民族のひとつであり、紀元前3千~2千年頃に欧州の中西部を中心に定住を始めたものと思われるが、民族的には不明なことが多い。紀元前7~3世紀頃には、現在のフランスとドイツ、北イタリアで活動した陸のケルトと、英国やアイルランドに渡った海のケルトとに分かれる。ジュエリー史上意味のあるのは海のケルトであり、その遺物の多くは英国やアイルランドから出土する。
装飾的かつ実用的なジュエリー
ケルト民族は金属の細工に優れており、金や銀、ブロンズなどを用いた多くの装身具や武器、実用具などが残っている。そうした遺物の最大の特徴は、ほとんど金属だけで作られたもので、宝石類の使用はまれなことだ。彼らが5~6世紀頃にキリスト教化する以前のジュエリーで最も特異なものは、用途不明の半月形の装身具ルヌラエとトルクと呼ばれるネックレスである。ルヌラエはきわめて薄い金で作られ、その縁にはジグザグの模様が刻まれている。トルクは、太い金の筒状のものを撚り合わせて作られており、円形の一部が開いた形で、その両端には飾りがある。
また広くはフィビュラと呼ばれる安全ピンの形をしたブローチも、ケルトの創案のものだ。
これはヴァイキングやアングロサクソンのジュエリーにも見られるが、元来、衣服の合わせ目を留めるための実用具であった。ボタンはまだ存在しないこの時代、北の寒冷地にあって、厚手の外套は不可欠であり、フィビュラは必需品であったに違いない。事実、その後も形は変わるがケルト人のジュエリーとして作られ続ける。
キリスト教が影響を及ぼし始めた以後のジュエリーには、ヴァイキングのグリッピング・ビーストに似た、つなぎ紐状のパターンが登場する。たとえば、不完全円のブローチと呼ばれる丸い輪の一部が途切れたデザインで、ピンが固定されておらず円形の上を移動する不思議な形状のものに使われている。装飾的には優れたものだが、これもまた実用品であったに違いない。これは、19世紀にスコッティッシュ・ジュエリーと呼ばれる安価な製品がスコットランドやアイルランドの観光土産としてロンドンに持ち帰られる頃になっても、ケルトの代表的なデザインとして使われている。
アングロサクソン【今日の英国人の祖先となった民族の質実剛健な金属工芸の遺物】
英国本島の文化の礎を築いた民族
アングロサクソンとは、5世紀から6世紀にかけて、北ドイツ方面から現在の英国本土に侵入してきた、ゲルマン系のアングル人とサクソン人を言う。彼らは6世紀頃からキリスト教化し、10世紀頃にこれまた北欧からのデーン人の侵略を受けるまで英国本島に拠って諸王国を築き、その他の文化を担った民族である。今日の英国人の祖先のひとつでもある。キリスト教化以前の彼らは、多くの金属工芸の遺物を残している。今でも英国内から発掘されるそれらは、古くはケルトの、近くはヴァイキングやゲルマン諸族の強い影響を受け、類似性が見られる。
さまざまなブローチの存在が示す生活様式
アングロサクソンのジュエリーの一番の特徴は、実に多様なブローチの存在である。これはケルトやヴァイキングなどと同様、一種の実用具として発達した。素材も金と銀、ブロンズで、宝石の使用がきわめて少ないことも共通している。ただし、アングロサクソンの場合には、ディスク・ブローチと呼ばれる円形のものが中心で、これに不完全円のものと十字架のものとが加わる。ディスク・ブローチは完全な円形のもので、裏面に直径の半分ほどの短いピンが付いている。表面はさまざまで、銀と銅に鉛と硫黄を加えて作る鈍い鼠色のニエロで紐帯模様が付けられたものや、時代が下がると線刻でキリスト像などを入れたものがある。また一部には金線による縦枠が付けられ、その枠内にガーネットや七宝などが埋め込まれたものもある。十字架状のブローチとは、十字架というよりも縦軸の上部の幅の広い横軸が付いた形、あるいは四角頭のブローチとも言われるように、縦軸の上に四角の部分が乗っかっただけの奇抜な形状のもので、どういうわけか中央部丸くブリッジ状に湾曲している。表面の模様はディスク・ブローチとあまり変わらない。ブローチのなかでは最も奇抜なデザインのものだ。
激しく活動した民族のせいかベルトのバックルも多く、複雑な紐帯模様のもがサットン・フーの遺跡から出土している
ヴァイキング【縦横無尽に船を操り外海をも往来した海洋民族の不思議なデザイン文様】
優れた航行能力をもった海洋民族
8世紀の末から11世紀にかけて、今日のノルウェーやデンマーク、スウェーデンなどに居住しながら、北海沿岸や英国、アイルランド、アイスランド、さらにはスペイン沿岸を経て遠くコンスタンチノープルにまで足跡を残した海洋民族を言う。その目的は海賊行為と書く本もあるが、それだけではなく、通常の交易も目的であり、ヴィキング船と呼ばれる長く先端の尖った船をあやつり、大西洋横断を行うほどの航行能力を持った。
ヴァイキングの独自のデザイン
その美術様式の初期のものは、北方の土着文化がケルトの影響を受けたもので、後期の5~7世紀頃からはゲルマン美術と共通項の多いものとなる。
ヴァイキングが残したジュエリーの多くはケルトの影響を受けたもので、さらに北方ゲルマンあるいはアングロサクソンのものに酷似しているという特徴を持つ。歴史的な経過をたどれば当然ということだが、ヴァイキングのものにしかない特徴と言えるのは、グリッピング・ビーストと呼ばれるデザイン・パターンだ。ビースト(獣)の名ごとくこれは動物文の一種で、複数の動物(何であるかは特定できない)が手足を結びあった形で表現され、さらに進むと、紐が無限に絡みあったような不思議な文様となる。紐なのかとよく見ると、先端の部分に動物を思わせる目が描かれていたりして驚く。
ジュエリーの中心は、やはりブローチである。だが、時代が新しいせいもあるのかいわゆるフィビュラ形式のブローチはほとんど見られず、特有の円盤形式のものが中心となる。まれに楕円形のものもあるが、これは肩の所に用いて外套が落ちないようにしたものだ。その表面をはい回るような動物文は、多くが金線を貼って輪郭を描いたフィリグリー細工で、他に類を見ないジュエリーと言えるだろう。
コロンブス以前にアメリカ以前にアメリカ大陸にまで到達するほどの航海術を持っていた民族にしては自己のスタイルに変化がなく、海賊行為や交易の相手らの影響がほぼ皆無な点も面白い特徴である。
騎馬民族の世界【家畜と共に移動する生活様式から生まれた他の民族には見られない独特な装身具】
広大な地域を騎馬で移動する生活
騎馬民族、英語でいうノマドとは、紀元前3千年頃から、黒海北岸から遠くモンゴルを経て日本海沿岸に至るまでの広大の地域を、馬に乗って駆け巡った多くの民族を言う。スキタイやサルマタイ匈奴、モンゴルなどさまざまな民族が行き来を繰り返し、その東端は朝鮮半島にまで及ぶ。彼らは定住せず、農耕にも従事せず、家畜と共に移動することを生活の基盤とした。したがい、その生活様式は他の諸民族との決定的に異なり、用いる道具類にも際立った特徴がある。彼らは装身することを好み、多くのジュエリーを作り、使った。
移動生活に密接に関連した装身具の数々
騎馬民族が使ったジュエリーには、共通項でも言うべき特長がある。デザイン面での動物文あるいは動物闘争文と、生活様式からくる他の民族には見られないような装身具類が多いことである。アップリケのように衣服に縫い付けるジュエリーと、バックルと言うか、ベルトの飾り物というか、その種の装身具だ。動物をデザインしたものは、黒海北岸の地域から遠くアルマアタ、さらにはシベリア地方にまで広がっており、彼らが衣食を共にする動物たちへの愛着とそれを襲う野生の動物たちへの関心を示す。その多くは金の板の打ち出しであり、技術的には難しいものではなく、また宝石類はほとんど使われていない。こうした彼らのジュエリーも、年代が下がるにつれて首飾りといった荘厳具に近いものも登場し、トルコ石やガーネットなどの宝石が使われるが、それは歴史の過程における他民族との接触の影響ではあっても、騎馬民族のジュエリーとしては本来のものではない。
先述のアップリケに似た装身具は必ず前後左右にいずれかに孔が開いており、これで衣服に縫い付けたのであろう。また、バックル類は、いわゆ胡服騎射と言われる生活様式にとって不可欠な、ズボンをはいて胴を締める服装からくる必然のものであった。こうした装身具の典型は、実は、隣の韓国に多くある。金製腰偑と呼ばれるものがそれで、ベルトそのものが金で作られ、そこからさまざまな実用品が様式化したデザインで吊り下げられている。これなどは、騎馬民族朝鮮半島にまで来た証拠ではなかろうか。ともかく、騎馬民族のジュエリーは一見に値する
まとめ
この記事ではヨーロッパ宝飾芸術の源流について解説してきました。
(エジプト・メソポタミア文明からギリシャそしてイタリアから西欧とステップ地帯)次は古典期から近世のヘレニズムから新古典主義について解説していきます。
